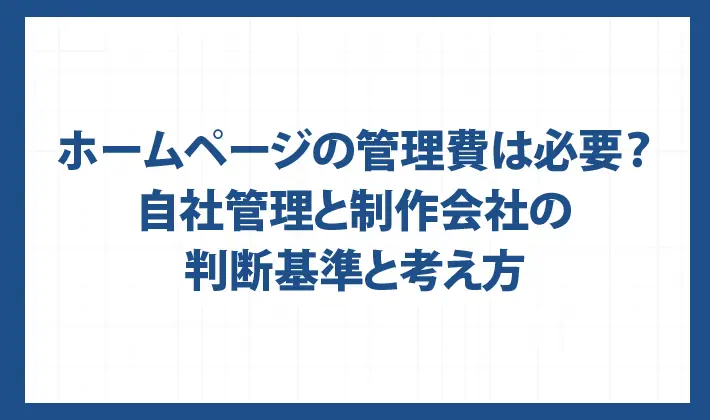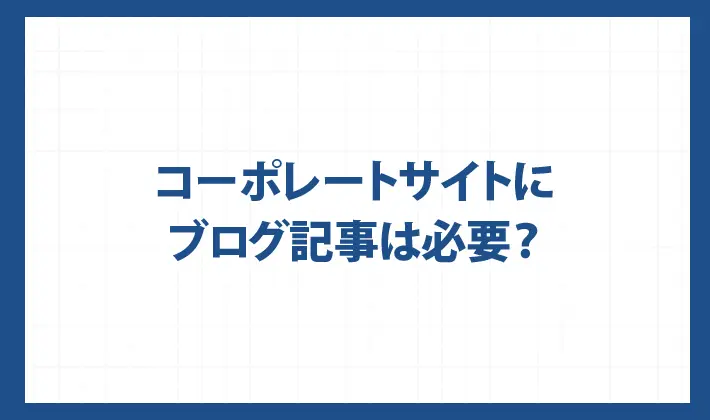
企業・会社のホームページでブログ記事を書くことは、新規見込み客を獲得するのに有効です。記事を書くためには「目的・素材集め・体制」を揃えることが大切です。
この記事では、会社のブログが自社に必要かどうかを簡単に見分ける方法を説明します。必要な場合は、最初に書く内容、始めの本数、公開の順番、問い合わせにつなげるための見せ方まで具体的に分かります。今は始めないほうがよい場合の進め方も紹介します。必要かどうか、いつ始めるか、始めるなら何をするかについてお伝えします。
目次
必要かどうかは「4つの条件」で決まる
企業が運営するホームページのブログは、条件がそろえばしっかりと役に立ちます。ここでは、始めるかどうかを決めるための4つの条件を順に説明します。むずかしい専門用語は使いませんので、自社の状況に当てはめてブログ記事が必要かどうかを判断してください。
4つのうち3つ以上に当てはまれば、今すぐ始める価値があります。二つ以下であれば、次章で紹介する代替の進め方から整えることが最短です。
条件1:目的がはっきりしている
ブログを通じて何をしたいのか一つに的を絞ります。問い合わせを増やすのか、会社名の検索を増やすのか、採用の応募を増やすのか、いずれかに絞ります。目的が一つだと、記事の内容がぶれず、効果の測り方も明確になります。
社内で「今回の目的は問い合わせを増やすことです」と言い切れる状態であればOKです。
条件2:材料(見せられる情報)がある
ブログを通じて何をしたいのか一つに的を絞ります。問い合わせを増やすのか、会社名の検索を増やすのか、採用の応募を増やすのか、いずれかに絞ります。目的が一つだと、記事の内容がぶれず、効果の測り方も明確になります。
社内で「今回の目的は問い合わせを増やすことです」と言い切れる状態であればOKです。
条件3:続けられる体制がある
更新を続けられるかが成果を左右します。月に2本のペースで6か月続ける体制を基準にします。社内で書く場合は担当と締切を決めます。外注する場合は費用とやり取りの流れを決めます。
来月分までの題材と締切が決まっている状態であればOKです。
条件4:次の行動につながる導線がある
記事を読んだ人がすぐに動けるように、問い合わせや見積依頼、資料ダウンロードに進めるボタンやリンクを記事の途中と最後に置きます。導線があると、読まれて終わりになりません。
記事の中とページ下部に、問い合わせや資料ダウンロードへ進むリンクが設置できればOKです。
ブログのメリットとデメリット
ブログが「有効」という意味は、新しい見込み客を検索から呼び込めること、問い合わせや資料請求につながりやすくなること、写真や数値を見せて信頼を高められること、商談前に疑問を減らして説明が楽になること、地域名と組み合わせて地元の方に届きやすくなることを指します。採用の場面でも、仕事の内容や雰囲気を伝えることで応募の質が上がります。
メリット
役に立つ記事を公開すると、広告に頼らなくても検索から安定して訪問者がアクセスしてくれます。写真や工程、費用の目安を示すことで仕事の進め方が具体的に伝わり、安心して問い合わせに進めます。よくある質問を記事にまとめておくと、読んだ方が事前に理解を深めるため、商談では本題に集中できます。一度評価された記事は長く読まれ続けるため、会社の資産として24時間働いてくれます。
デメリット
記事を用意するには時間と費用が必要です。企画から公開までには数時間から半日ほどかかり、結果が安定するまでには時間が必要です。更新が止まると不安な印象を与えるため、継続できる体制づくりが欠かせません。内容の正確さや写真の権利にも注意が必要です。サイトの設定が複雑になると読み込みが遅くなることがあるため、整理しながら進めることが重要です。
デメリットへの向き合い方
最初はテーマを絞り、同じ書き方の型で進めると負担を抑えられます。公開した後は、読まれ方を見ながら見出しの調整や図の追加、最新情報への更新を行います。月の本数を少なめに設定し、締切と確認の流れを固定すると止まりにくくなります。正確さが不安な内容は、社内の担当者が短く確認する仕組みを作ると安全です。
セルフ診断:あなたの会社は?
ここでは、今ブログを始めるべきかを短時間で判断できるようにします。むずかしい準備は不要です。次の問いを順に読み、頭の中で「はい」か「いいえ」で答えてください。
Q1. だれに何をしてほしいかを言い切れますか
問い合わせを増やす、資料ダウンロードを増やす、会社名での検索を増やす、採用の応募を増やすのいずれかを一つに決められるかを決めていますか。目的が一つに定まっていれば、記事の内容と見せ方がぶれません。たとえば「問い合わせを増やす」と決めた場合は、費用、比較、事例、よくある質問といった内容に集中できます。
Q2. 読者に見せられる材料はそろっていますか
実際の事例写真、費用の目安、作業の流れ、お客様の声、担当者のコメントのいずれかを公開できる状態ですか。これらの材料があると、記事の説得力が高まり、安心して次の行動に進めます。写真が少ない場合は、工程図や簡単な表でも代わりになります。
Q3. 月に2本、6か月続ける体制はありますか
更新の継続は成果に直結します。社内で書く場合は担当と締切を決め、レビューの流れを用意します。外注する場合は費用の上限、連絡方法、納品までの手順を最初に固めます。来月分までの題材と締切が決まっていれば、開始に必要な体制は整っています。
Q4. 読んだ後の行き先は用意できていますか
記事の途中と最後に、問い合わせ、見積依頼、資料ダウンロード、無料相談のいずれかへ進めるボタンやリンクを設置できますか。行き先が明確であれば、読まれて終わりにならず、実際の行動につながります。
判定の読み方
4つの問いのうち「はい」が3つ以上であれば、今始める価値があります。「はい」が2つ以下であれば、次章で紹介する代替の進め方から整えるといいです。必要性の判断がつかない場合は、目的を一つに絞るところから始めてください。
どの業種でも効く「勝ちパターン」
業種が違っても、読み手が知りたい順番に沿ってわかりやすく伝えることで大切です。ここでは、記事の基本の流れ、はじめに狙うと良い検索の切り口、すぐに使えるタイトル例を示します。初めての方でも迷わない形でお伝えします。
記事の型(テンプレ)
最初に結論を短く簡潔に書きます。次に、読者がいま抱えている不安や困りごとを具体例を踏まえて描きます。そのうえで、解決までの手順を順番に説明します。続いて、よくある失敗例と対策方法を挙げ、実際にかかる費用や期間の目安を提示します。別の方法やサービスとの違いを簡単な比較で触れ、最後に事例を紹介します。締めくくりに、問い合わせや資料ダウンロードに進める案内を置きます。この流れに沿うと、読み手は迷わず次の行動に進めます。
まず狙うキーワード
検索では、料金や相場、選び方、事例、失敗しないコツ、手順や流れといった言葉がよく使われます。地域で探す人には、地域名とサービス名の組み合わせが役に立ちます。例えば「福岡市 外壁補修 相場」「東京 清掃サービス 選び方」「製造ライン 改善 事例」のように、読み手が打ち込みやすい表現を記事タイトルや見出しに入れると届きやすくなります。
タイトル例
「【福岡市】外壁補修の料金と期間の目安|見積もりで損をしないための確認ポイント」
「初めての定期清掃ガイド|依頼の流れと準備しておく書類をわかりやすく解説」
「ケーススタディ:治具の見直しで不良率を下げた方法と費用の考え方」
「ロープアクセスと足場、どちらが向いているか|作業範囲とコストの違いを簡単に説明」
これから体制を整えるなら
今すぐブログを続ける体制が無い場合でも、準備は進められます。最初に整えるべきは、事例ページ、料金ページ、FAQの3つです。
事例ページでは、写真、作業前後の様子、費用の目安、かかった日数、担当者のひと言を順番に示します。読み手は自分の状況と照らし合わせやすくなり、問い合わせの不安が下がります。
料金ページでは、基本料金、含まれる範囲、追加費用が発生する条件、支払い方法を明確にします。見積もりの見方を短く添えると、比較検討の助けになります。
FAQでは、よくある不安を短い質問と短い答えでまとめます。におい、音、所要時間、保証、キャンセル条件、個人情報の扱いなど、問い合わせ前に気になる点を説明します。
これらのページは、広告を使わなくても自然検索からの流入に対応でき、営業の説明時間を減らします。リンクの置き方も重要です。事例から料金へ、料金からFAQへ、FAQから問い合わせへと進める流れをページ内の文脈に合わせて配置します。最初の仕上がりは完璧でなくて構いません。後から写真を追加し、表現を分かりやすく直し、最新情報に入れ替える前提で公開します。公開日と更新日を表示し、更新の履歴を残すと、信頼が高まります。
失敗しない始め方(5ステップ)
ブログを始める場合は、最初の設計が大切になります。ここでは、初めてでも迷わず進めるための5つの手順を順番に説明します。
Step1:目的をひとつに決める
問い合わせを増やす、資料ダウンロードを増やす、指名検索を増やす、採用の応募を増やすのいずれかに絞ります。目的がひとつになると、見出しの選び方、写真の使い方、ボタンの置き方まで判断がそろいます。たとえば問い合わせを増やす目的なら、費用、比較、事例、FAQを中心に据えます。
Step2:柱記事と周辺記事を決める
大きな全体説明を担う柱記事を1本用意し、その周りに具体的な悩みに答える周辺記事を並べます。柱記事では、基本の考え方、流れ、費用の見方、よくある質問への入口をまとめます。周辺記事では、症状別、用途別、地域別など、読み手が検索に使いやすい切り口で詳しく解説します。柱から周辺へ、周辺から柱へ内部リンクを置くと、関連する記事を読んでくれます。
Step3:同じ型で書く
各記事は、結論、読者の悩み、解決の手順、失敗例、費用と期間、別の方法との違い、事例、次の行動という流れで統一します。型をそろえると、執筆も編集も早くなり、読み手も迷いません。写真や数字は各章に少なくともひとつ入れ、見出しの直後に要点を短く添えます。
Step4:導線を記事内と末尾に置く
読み手が次に進めるように、記事の途中と最後に問い合わせ、見積依頼、資料ダウンロード、無料相談のリンクやボタンを置きます。文脈に合う箇所に自然に差し込み、押した先で必要な情報がすぐ読めるように関連ページへつなぎます。電話番号や営業時間の表記も忘れずに載せます。
Step5:公開後に計画的な見直しを行う
公開して終わりではありません。3〜4週間後に読みやすさ、検索で使われた言葉、離脱の多い箇所を確認し、見出しの言い回し、図の追加、説明の順番を整えます。順位が動き始めた記事は厚くし、動きが少ない記事は切り口を見直します。新規公開ばかり増やすのではなく、見直しの回数を増やすと成果が安定します。
最初の8記事:そのまま使えるテーマ例
最初の段階では、読者が知りたい順番に合わせて8記事を用意すると迷いません。ここでは各テーマの狙いと、どのような内容を入れると良いかを順に説明します。専門用語は避け、写真や数字を最小限でも入れる前提で進めます。
料金と相場のかんたん早見表
読者が最初に知りたいのは費用の目安です。作業の種類や規模、よく発生する追加費用、支払いのタイミングをわかる言葉で説明します。金額は幅で示し、どの条件で上下するのかを理由と一緒に伝えます。最後に見積依頼への案内を置くと行動につながります。
タイトルの例
「【地域名】〇〇の料金と相場|追加費用が発生する条件までやさしく解説」
失敗しない業者選び
読者は比較の視点を求めています。資格の有無、保証の範囲、見積書で確認すべき点、契約前の注意事項を順番に示します。実物の見積書サンプルがあれば、重要箇所を指でなぞるように説明します。
タイトルの例
「失敗しない〇〇業者の選び方|見積書で見るべき3つのポイント」
はじめての流れと準備
問い合わせから作業完了までの道筋を、時系列で説明します。読者が用意すべき情報、当日の持ち物や服装、よくある質問への短い答えを入れると安心感が高まります。
タイトルの例
「はじめてでも安心の〇〇ガイド|問い合わせから完了までの流れと準備」
事例(写真・費用・期間つき)
実際の変化は説得力につながります。作業前後の写真、依頼の背景、提案の理由、かかった費用と日数、完了後の様子を一つの物語として示します。最後に同じ悩みの方へ向けた案内を添えます。
タイトルの例
「事例|〇〇でここまで改善|費用△△円・期間□□日」
比較記事(別の方法との違い)
別案を知ることで納得が深まります。代表的な方法を二つ取り上げ、費用、期間、安全性、対応できる範囲の違いを同じ観点で説明します。どの条件ならどちらが向くかを結論として示します。
タイトルの例
「〇〇と××はどちらが向くか|費用と期間の違いをやさしく説明」
トラブルQ&A
問い合わせ前に心配になる点を先まわりで解消します。におい、音、近隣対応、雨天時、保証、キャンセルの条件を短い質問と短い答えで並べ、必要なところに詳しい記事への案内を置きます。
タイトルの例
「よくある質問|におい・音・保証・キャンセルまでひとつずつ回答」
地域名×用途の案内
地元で探す読者には地域名が手がかりです。地域ごとの規模感や現場の特徴、対応できる時間帯、移動費の扱いなどを説明し、近い事例があれば合わせて紹介します。
タイトルの例
「【地域名】で〇〇を頼む前に知っておきたいこと|地域の事情と事例」
まとめ
上記7記事の要点を一つの長いページで振り返り、必要に応じて各記事へ進めるようにします。最初に結論を置き、途中で費用、流れ、比較、事例、Q&Aの順に案内する構成にすると、全体像がつかみやすくなります。
タイトルの例
「はじめての〇〇完全ガイド|費用・流れ・比較・事例・質問まで総まとめ」
効果の測り方
成果を確かめる方法は複雑ではありません。記事ごとの訪問数、検索で使われた言葉、問い合わせや資料ダウンロードの件数、読まれ方の深さの4つを定期的に見れば充分です。公開から3〜6か月で順位の動きが現れ、6〜12か月で問い合わせの安定につながります。
記事ごとの訪問数
どの記事にどれだけ人が来ているかを見ます。増えている記事は見出しや写真の追加で情報量を増やします。伸びが弱い記事はタイトルの言い回しを見直し、読者が使う言葉に合わせます。
検索で使われた言葉
実際に検索された言葉を確認し、本文の見出しに取り入れます。読み手の表現にそろえることで、ずれを小さくできます。想定外の言葉で見られている場合は、段落を一つ追加して答えを補います。
問い合わせや資料ダウンロードの件数
行動の数は最も重要です。記事の途中と最後の案内が機能しているかを確かめ、押した先のページで迷わない構成かどうかも確認します。案内の言葉は、読者の不安を一つだけ解消する表現にします。
読まれ方の深さ
ページの下まで読まれているか、途中で離脱していないかを見ます。離脱が多い箇所は、図や写真の追加、段落の入れ替え、言い回しの短縮で改善します。読みやすさの調整は効果が早く現れます。
よくある失敗と回避策
運用のつまずきは似ています。ここでは、起きやすい失敗と直し方を対にして説明します。言い換えと順番の見直しだけで解決するものが多く、特別な知識は必要ありません。
社内ニュースに偏ってしまう
イベント報告やお知らせだけでは検索に届きません。読者の困りごとに合わせ、費用、比較、手順、事例の順に並べ直します。社内ニュースは会社案内にまとめ、ブログでは悩み解決を主役にします。
写真や数字がなく説得力が弱い
言葉だけでは不安が残ります。作業前後の写真、費用と日数、担当者の短い説明を最小限でも入れます。写真が難しい場合は図や簡単な表で代わりにします。
更新が止まってしまう
止まる理由は題材と締切が決まっていないことです。月2本を上限にし、担当、題材、締切、確認者を先に決めます。公開後の見直しの予定日も同時に入れておくと、次の動きが止まりません。
案内のボタンやリンクが弱い
読まれて終わりになる原因です。本文の途中と最後に案内を置き、押した先のページで必要な情報にすぐ届くようにします。電話番号と営業時間の表記も近くに置くと行動しやすくなります。
似た内容の記事が増えて順位が分散する
同じテーマが複数あると評価が割れます。内容が近い記事は一つにまとめ、古いページは新しいページへ案内します。検索の言葉は一つのページに一つずつ割り当てると整理できます。
あなたの現状は・・・
始めるかどうかは、目的、材料、体制、導線の四つで判断します。三つ以上そろっていれば、今から始める価値があります。二つ以下であれば、事例、料金、FAQの三つを先に整えることが最短です。始めると決めた場合は、柱記事と周辺記事を決め、同じ型で書き、記事内と最後に案内を置きます。公開後は計画的に見直し、読者の言葉に合わせて更新します。以上の流れで、読者の不安は解け、問い合わせや資料ダウンロードにつながります。